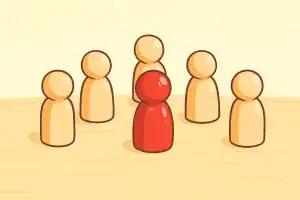医療事務は安定性や専門性のある仕事として人気ですが、実は「すぐ辞めてしまう人が多い職種」でもあります。
本記事では、そんな離職傾向の背景と、よくある5つの特徴、さらに辞めずに続けるための具体的な対策を解説します。
医療事務はなぜ早期退職者が多いのか?
医療事務の仕事は一見、安定していて座ってできる事務職に見えますが、実際は「同じ作業の繰り返し」かつ「人との関わりが多い」仕事です。
毎月決まった時期に行うレセプト業務、受付での対応、電話・院内連携など、単調さと忙しさが同居しており、適性が合わないと「想像以上にしんどい」と感じてしまう人も。
ただし大事なのは「早く辞めた=向いていない人」とは限らないということ。
向き・不向きや環境の違いが大きく影響しており、自分に合った職場や準備があれば継続可能な職種です。
医療事務をすぐ辞めてしまう人の特徴5選
1. 人との会話が苦手で接客に疲れやすい人
医療事務は受付業務・患者応対・職員とのやり取りなど、人間関係が仕事の大部分を占めます。
会話が苦手な人は、患者からのクレームや同僚とのやり取りにストレスを感じやすく、孤立してしまう可能性も。
特に人間関係の悩みは離職理由として非常に多いため、「接客が苦にならないか」は重要な判断ポイントです。
2. 「楽そうだから」と安易に医療事務を選んだ人
「資格があれば簡単にできる」「座ってできるからラクそう」などのイメージで選ぶと、現実とのギャップで挫折しやすくなります。
医療事務は覚えることが多く、慣れるまでに時間がかかる仕事です。
「資格がある=即戦力」ではなく、実務経験や地道な勉強が必要だという理解が不可欠です。
3. マルチタスクが苦手な人
受付しながら電話が鳴る、他の患者の案内を同時にこなす、スタッフからの声かけに対応する…。
こうした複数の業務を並行処理する状況は日常茶飯事です。
瞬時に優先順位をつけて動けるか、周囲の動きに注意を向けられるかが、働きやすさを大きく左右します。
4. 体力に不安がある人
事務職とはいえ、座りっぱなしではありません。
立ち上がって受付に案内したり、診察室と受付を何度も往復したりと、意外と身体を使う場面が多いのが現実です。
特にクリニック勤務では人数が少ないため、事務も清掃も業者対応もすべてこなすケースも。
40代以降は「思ったより疲れる」と感じる方も多くなります。
5. 緊急時に落ち着いて対処できない人
医療現場では、イレギュラー対応が突然起こります。
「薬の説明がわからない」「診察の順番を変えたい」「救急患者が来た」など、パニックにならずに冷静に判断する力が求められます。
その場しのぎの対応ではなく、全体を見て判断し、医師や看護師と協力して行動する冷静さがカギになります。
おまけ
その職場のお局さんと上手くいかない。実はよくあるケースです。
「すぐ辞める=向いていない」ではないという真実
医療事務を早期に辞めた人の中にも、高い能力やポテンシャルを持っている人は多いです。
たまたま配属先の人間関係、業務環境が合わなかっただけで、他職場なら続けられるケースも珍しくありません。
大切なのは、「向いていない」と決めつけず、自分の性格や価値観に合う働き方を探ること。
医療事務以外にも、自分に向いている職種が必ずあります。
実は「知識不足」が原因のケースもある
5つの特徴に当てはまらないのに辞めたくなった場合、診療報酬やレセプト業務への理解不足がストレスの原因になっていることもあります。
知識が増えることで、
- 作業に余裕が生まれる
- 自信がつく
- 周囲とのコミュニケーションがスムーズになる
といった好循環が起こります。
例えば、「診療報酬請求事務能力認定試験」などの資格取得を目指すことで、理解力と実践力が向上し、働きやすさが大きく変わります。
結論|医療事務を辞める前に知っておきたいこと
✔ 合わないと感じた理由を整理する
✔ 知識不足や環境の問題かもしれないと視点を変える
✔ 「向いてない」ではなく「今の職場が合わなかった」可能性もある
✔ 続けるか辞めるかは、情報と経験を積んでから決めても遅くない
こんな人は再チャレンジの価値あり
- 少しずつ知識をつけて成長していくのが好きな人
- 人と関わる仕事にやりがいを感じる人
- 自分の努力で職場をより良くしたいと考える人
医療事務は「合えば天職」と言われることも多い仕事です。
すぐ辞めてしまいそうな自分を責めず、「どうすれば続けられるか?」の視点に切り替えてみませんか?