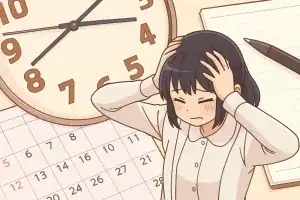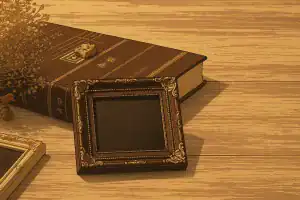「心がモヤモヤして、落ち着かない」 「理由はわからないけど、不安が頭から離れない」 そんな、なんとなくの不安に悩まされていませんか?
このような不安は、誰にでも起こり得る自然な心の反応です。 しかし、放っておくと日常生活に支障をきたし、ストレスや慢性的な疲れに繋がることもあります。
本記事では、哲学者の視点と心理学的アプローチをもとに「不安を感じたときにできる対処法」を7つ紹介します。 職場や家庭、人間関係に悩む方、HSP(繊細さん)の傾向がある方にも参考になる内容です。
不安を軽くするためにまず知っておきたいこと
不安は「生きている証拠」である
不安は、あなたの心が「何か大切なものを守りたい」と思っている証です。 心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求5段階説」では、不安は「安全の欲求」や「承認の欲求」に深く関係していると思います。
哲学者が語る、常識と不安の関係
哲学者・中村雄二郎は『術後集』の中で「常識は地域と時代が生み出す自己解釈的な共通感覚にすぎない」と述べています。また、哲学者・三木清は「常識に疑問を持てる知恵が良識である」と。
つまり、不安は「周囲の常識に無理に自分を合わせているとき」にも生じやすく、そこに気づくことが第一歩です。
不安感をやわらげるための7つの方法
1. 不安の正体を「言語化」
ぼんやりとした不安ほど、私たちを強く支配します。 まずは「なにが不安なのか?」を紙に書き出して、言葉にしましょう。
2. 「今ここ」に意識を戻す
不安は未来に対する感情です。 今に集中することで、その感情から少し距離を取ることができます。 おすすめは、呼吸に意識を向ける・香りを嗅ぐ・音楽を聴くなど五感を使ったマインドフルネス。
3. 良識を基準に行動を見直す
「みんながそうしているから」ではなく、「自分の良心に照らして納得できるか?」を判断軸にしましょう。 他人の承認ではなく、自分の価値観に沿った生き方が、不安を減らします。
4. 承認欲求の罠から距離を置く
「評価されたい」「認められたい」と願うこと自体は自然です。 しかし、それが度を超すと、自分で選ぶ人生が奪われてしまいます。 SNSや会社など、承認を軸にした世界から定期的に距離を取る習慣を持ちましょう。
5. 不安になったときの「安心ルーティン」を作る
例えば、決まった音楽を流す、温かい飲み物を飲む、アロマを焚くなど。
「これをすれば落ち着ける」という体験を身体に覚えさせることで、不安時のセルフケアがしやすくなります。
6. 安心できる「人間関係」を意識的に選ぶ
不安を和らげる一番の薬は、安全であるつながりです。 疲れる人と無理に関わる必要はありません。 自分の感情を尊重してくれる人との関係を大切にしましょう。
7. 「自分で選ぶ」小さな行動を積み重ねる
朝食の内容、帰り道、読む本、SNSでの発言。 どんなに小さなことでも「自分で選んだ」という感覚は、自信と安心感を育てます。
まとめ:不安は目覚めのサイン
不安を感じることは、心がまだ生きている証拠です。 そしてその不安は、あなたが「ほんとうの自分に戻りたい」と願っていることの表れかもしれません。
常識に従うだけではなく、自分の良識に従って選択する。 その一歩を踏み出すことで、不安に支配されず、自分らしい人生を歩む力が湧いてくると思います。