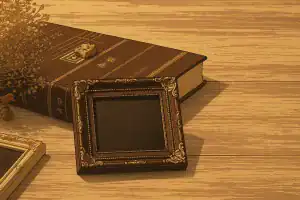人々は理解できないことを、低く見積もる。
この言葉は、ドイツの詩人であり思想家であるゲーテのものとして知られています。
私も、理解できないことを、つい価値がないと思いがちです。
確かに、自分の理解の及ばないものを無意識に「価値が低い」と判断してしまう傾向にあるような気がします。
でも、果たしてそれは本当に「価値がない」のでしょうか?
たとえば、現代アート。
カンバスに一滴の絵の具が垂らされているだけの作品に「こんなものが芸術だなんて」と首をかしげた経験はありませんか?
しかしその裏には、アーティストのみえない試行錯誤や、社会や自分自身に対するメッセージが込められていることもあるのです。
理解できないものを「つまらない」と考えてしまうのは、視野を狭くする行為となってしまいます。
理解できないものには、しばしば「時間」が必要です。
初めて出会った思想や価値観にすぐ馴染めなくても、それはあなたの感性が劣っているわけではありません。
ただ、まだその背景や文脈を十分に知らないだけ。誰もが最初は初心者です。
理解とは、咀嚼と熟成のプロセスの中で育つもの。
そしてこれは、人間関係にも言えることです。
他人の行動や考え方が理解できないとき、私たちはしばしば距離を置いたり、否定したくなります。
でも、見えているのはその人の一部でしかなく、その背景には複雑な人生や経験があるかもしれない。
「理解できない」ではなく「まだ知らない」と捉えることができれば、人との関係もぐっと深まるかもしれません。
ビジネスの世界でも同様
革新的なサービスやプロダクトが登場したとき、それがなぜ価値があるのかをすぐには理解できないことがあります。
かつて、インターネットやスマートフォンでさえ、最初は「意味がない」と言われたことがありましたよね。
それでも、世界を変えた。理解は、後からついてくることもあるのです。
自分を守るための反応
「理解できないことを低く見積もる」という心のクセは、ある意味で「自分を守るための反応」かもしれません。
未知のものに出会うとき、人は不安を感じます。そしてその不安を打ち消すために「これは価値がない」と判断してしまう。
でも、そこにこそ、自分の世界を広げるヒントが隠れているのかもしれません。
私たちは「理解すること=すべてを把握すること」と思いがちですが、実は理解とは「尊重の入り口」にすぎないのです。
自分とは違う何かを、そのまま受け入れる柔らかさ。
それが、これからの社会においてもっとも大切な力なのかもしれません。
無知を恥じるのではなく、謙虚さを持て
ゲーテの言葉に立ち返るとき、それは「無知を恥じるのではなく、謙虚さを持て」と私には感じました。
すぐにはわからないもの、すぐには共感できないこと。
そこに対して「否定」ではなく「敬意」を持つこと。
それが、より豊かな知性と感性につながっていくのではないでしょうか。