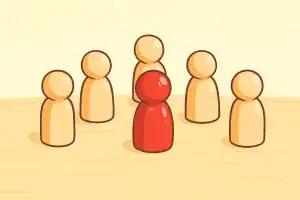はじめに
「毎日終電で帰る」「週末も疲れて寝るだけ」そんな生活が続いていませんか?
現代の働く人にとって、残業は避けがたい問題の一つ。しかし、慢性的な残業は心身に悪影響を及ぼすだけでなく、人生の質をも大きく低下します。プライベートにも影響しますし。私も残業が多い会社にいた頃があって心身ともに疲弊した時期があります。その時は辛かった。今振り返ると良い教訓です。
この記事では、残業が多い原因を明らかにし、どうすれば減らせるのか、そして最終的に転職という選択肢も含めて考えてみます。
残業が多い原因とは?
業務量が多すぎる
慢性的な人手不足や業務の属人化により、仕事量が一人に集中してしまうケースがあります。特に派遣社員があんまり働かなくて、正社員の方が頑張りすぎているとかありますよね。
職場の文化・上司の影響
「上司が帰らないから自分も帰れない」「残業が評価される」など、企業文化によって残業が常態化している職場もあります。圧の強い上司が、仕事はできるけど、残業しているとなかなか帰りづらいものです。
タイムマネジメントがうまくいっていない
優先順位のつけ方が甘く、やるべき仕事に集中できず、残業が増えることありますね。特に注意散漫になりがちな方は要注意!
残業によるデメリットとリスク
心身への悪影響
長時間労働はストレスや疾患の遠因になりやすく、健康リスクも高まります。寝る時間も短くなったり、それで体への負担も増えますし、悪循環ですよね。
プライベート時間の喪失
家族や友人との時間、自分自身のリフレッシュ時間がなくなり、孤立感や無力感を感じやすくなります。家族に愚痴を言ったり相談する時間もなくなるので余計にストレスがたまっててしまう。
生産性の低下
疲労が蓄積することでミスが増え、かえって仕事効率が落ちる悪循環に陥ります。集中力が低下してしまうと仕事も捗らないですよね。
残業を減らすための実践的な方法
業務の優先順位を見直す
重要でない仕事に時間を使いすぎていないか確認し、ToDoリストで整理しましょう。私は元々優先順位をつけるのが苦手なタイプなので、仕事前の朝には、その日の仕事の優先順位をつけています。その日にしなくても良い仕事とかありますよね。
定時退社を習慣化する
毎週1日は「ノー残業デー」を作るなど、自分にルールを設けるのも有効です。自分で時間を強制的に区切るヤツです。もう、その時間からは仕事から離れるようにしています。
周囲とのコミュニケーションを変える
自分の業務量を適切に報告し、助けを求めることで業務の分担を見直せることもあります。やはり、人に任せることが大事です。私は、元々人に任せることが苦手でした。でもこれだと自分を追い詰めちゃうので、最近は任せられる仕事は任せるようにしています。
働き方改革と制度を活用しよう
フレックスタイム制やリモートワークの活用
会社によっては、柔軟な働き方を取り入れているところがあります。そうすると、効率よく仕事を進めることが可能になります。私の会社は、リモートワーク可能ですので週に2回は家で仕事しています。
有給休暇の取り方と制度の確認
休暇取得のハードルを下げ、しっかり休むことが長期的な生産性向上につながります。以前は、有給取ると罪悪感を感じたりしていましたが、最近は積極的に活用。リフレッシュしています。
会社の労働時間管理の実態をチェック
労働基準法や社内の就業規則を見直し、自分の働き方が正しいのかどうか確認しましょう。月の残業時間って多すぎたりしませんか?
どうしても無理なら転職も選択肢
転職を考えるタイミング
体調を崩したとき、改善の見込みがない職場なら転職を検討するタイミングです。結局、人間関係のストレスですと、転職するしかない時はあると思う。所属部署の人間関係が原因だと、配置転換してもらうと良いですが、実情はなかなかすんなり配置転換してくれる会社は少ないように思います。
働きやすい職場を見つけるポイント
残業時間の公開、柔軟な勤務制度、企業文化などをチェックしましょう。有給はちゃんととれるか?私は、企業の口コミサイトとかみています。社員、元社員の声はかなり参考になります。あともう一つ、実は採用前の面接官の態度も重視しています。面接官の態度がどうか、高圧的ではないか、質問内容は的確か。入社を急がすプレッシャーはないか?「誰でもよい」はないかとかでしょうか。それっておそらくその会社の雰囲気を表しているでしょうから。
キャリア相談サービスの活用
一人で悩まず、専門家に相談することで、自分に合った働き方の道が見つかります。本来は、自分の適性診断、自分の強みとか探してもらえるともっと良いと思いますよね。意外な発見があったりしますよ。
おわりに
あなたの残業は本当に必要なものでしょうか?今の働き方に疑問を持ったなら、一度立ち止まって考えてみてください。人生長いですが、いつでもチャンスを逃さないように頭の片隅にでも置いておいてください。