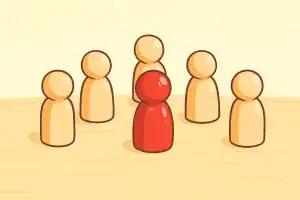はじめに:フルリモート=楽、ではなかった
新卒の子が会社に入ってきた。私の現在いる会社はフルリモートなので、おそらく新卒の子は困っていると思う。
知らない人は「在宅勤務って楽そうでいいね」
というかもしれない。
実際、通勤時間で疲れない、服装も自由、時間も融通がききますよね。家事、育児とかあると両立できるし。
確かに魅力的です。
でも、新卒でフルリモート勤務を始めた人たちのリアルは、世間が思っているよりずっとシビアなはず。
この記事では、現在フルリモートの私が感じた「リモートワークの本当の難しさ」と、
特に新卒にとっての落とし穴、そして企業側がすべき対策について、具体的に考えてみようと思う。
新卒がフルリモートで潰れる理由
世間では「新卒でリモート勤務=サボる」と思われがちだが、現実はまったく逆だ。
実際には、サボるどころか、病んでしまう人の方が多い。
なぜか?
理由はシンプルだと思う。
「仕事の進め方がわからないのに、誰にも相談できないから」
オフィスなら、誰かが雑談ついでに気づいて声をかけてくれる。
表情や雰囲気から「困ってそうだな」が読み取れる。
でも、リモートでは誰も困っていることに気づかない。
新卒にとって分からないことを相談するのは、そもそも勇気がいる。
それがSlackやTeamsなど、チャットでのやり取りになると、さらに心理的ハードルが上がる。
「何をどう聞けばいいか分からない」という悩みすら、相談できなくなる。
サボる余裕すらない、迷子のまま潰れる
「どうすればいいか分からない」状態が続くと、人は行動よりも思考に閉じこもる。
・Slackの文面を30分悩んで結局送信できない
・タスクが進まず、寝ても覚めても罪悪感だけが残る
・報告する内容がないこと自体がプレッシャーになる
結果、自分が仕事をしているという実感がなくなり、自己肯定感が急速に下がる。
この働いてる感の喪失が、新卒にとって最も危険だと思う。
どんなにやる気があっても、自信がボロボロになった状態では、モチベーションを保てない。だんだん消耗していく。
フルリモートは「自走できる人向け」の働き方
リモートワークは、裁量が大きい。
だからこそ、自分で考えて動ける人にとっては最高の働き方だ。
一方で、これまでチームで動く経験が少ない新卒にとっては、
「何をすべきか自分で決める」ことが、そもそも難しい。
・ゴールが見えない
・フィードバックが届かない
・小さな不安が積み重なる
つまり、フルリモートは未経験者にとって高難度モードだ。しかも、画面越しだと、なかなか相談しにくいです。
これは、本人の能力ではなく、単に構造の問題だと思う。
新卒がリモートで育つために必要な3つのこと
では、どうすれば新卒でも安心してリモート勤務ができるのか?
私の会社では、トライ&エラーの末に次の3つを徹底したことで、新人の離脱率が激減したそうだ(上司に聞いた)。
1. 「なんでも聞いてね」をやめて、先に聞く文化をつくる
新卒に「聞いてね」と言っても、そもそも何が分からないか分からないことが多い。
だから、先輩からの声かけルールを設け「困ってる前提」で接することで安心感を確保した。
2. 成果ではなく過程を見てフィードバックする
リモートでは成果しか見えにくいが、そこに至るトライアンドエラーのプロセスを認めることが重要。
日報や雑談チャネルを通じて、プロセスの共有と承認の場を増やした。
3. 「相談しやすいフォーマット」を固定化する
「ホウレンソウしよう」にとどまらず、相談テンプレートを作った。
たとえば:
- 相談背景(何をしていたか)
- 困っていること(何がつまずいたか)
- どうしたいか(自分の考え)
確かに、この3点を埋めるだけで、チャットでの相談ハードルが一気に下がる気がする。
リモートワーク時代こそ「育成設計」が命
リモートワークは、決して放任主義とイコールではない。
むしろ、介入のタイミングとつながり方の工夫がないと、新卒はすぐに孤立すると思う。
在宅でのびのび働くには、
「信頼」「承認」「コミュニケーションの仕組み」が不可欠だ。
そして会社側がその設計を怠れば、どんなにポテンシャルのある新卒でも、
ただ静かに、誰にも気づかれずに潰れていってしまうよね。
まとめ:フルリモートはプロ仕様の働き方。だからこそ「守る仕組み」が必要だ
リモートワークは、今後ますます広がっていくだろう。
でもそれは、全員が同じように適応できるわけではない。
特に新卒には、新卒なりの学び方、育て方がある。
もしあなたがこれから新卒を迎える側であるなら、
「自由にしていいよ」ではなく「安心して頼っていいよ」と言える仕組みを、
どうか、あらかじめ用意してあげてほしい。