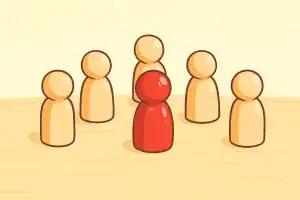「頑張った人」が損をする職場に、未来はあるのか
「お先に失礼します!」
時計が午後6時を指した瞬間、笑顔で席を立つ同僚たち。彼女たちの声は、事務所の空気を一瞬和らげるようにも見えた。でも
「……あ、はい。」
その場に残された私は、あいまいな返事を口にするだけで、画面から目を離せなかった。なぜなら、まだ山のような未処理ファイルがデスクに積まれているからだ。
いつの間にか「真面目にやる人」だけに増えていく仕事量
私の部署の仕事は、もともと4人分だった。それが気づけば3人に減らされ、さらに1人は「定時で帰る主義」を貫くようになって、実質2人で4人分の業務を回している。
いや、正確に言えば、「私が、ほぼ一人でやっている」。
同僚が帰ったオフィスで、私は無意識に歯ぎしりをしていた。頬の筋肉がピクピクと痙攣するのを自覚して、それでも「これが社会人ってものよね」と、自分に言い聞かせるしかなかった。
「あの子、ちょっと空気読めないよね」なんて言葉が飛ぶ前に
翌日、あの子の行動が話題にのぼった。
「彼女、わかってないのよね……。毎日定時で帰るの、さすがにないと思わない?」
もう一人の同僚も相槌を打つ。
「明日、ちゃんと注意した方がいいわね。」
ああ、始まった。
なぜ「定時で帰る」という、本来あるべき行動が、責められなければいけないのだろう?
どうして「頑張っている側」が、さらに頑張らなければならない空気を背負うのだろう?
「4人分の仕事を3人でやってるのに、補充もされない」
そのときのセリフが、胸に刺さった。
「4人分の仕事、3人でしてるんだから、人事部もうちょっと補充してくれないかしら。」
そう、正論なのだ。
でも正論を言ったところで、上は動かない。なぜなら、現場が、なんとか回ってしまっているから。誰かが黙って残って、穴を埋めてしまっているから。
頑張りすぎた人が、静かに心を壊していく構造
「真面目な人ほど、燃え尽きてしまう」
そんな言葉を、最近よく耳にする。私たちは「責任感がある」「空気が読める」「自分を犠牲にできる」人を、無意識のうちに使える人材として称賛する。
けれどそれは、同時に「何も言わずに引き受けてくれる便利な存在」として、都合よく消費しているだけかもしれない。
「定時で帰る人」が悪いのではない
誤解してほしくないのは、定時で帰るあの子が「悪い」わけではないということ。彼女は自分の契約通りに働き、時間を守って帰っているだけ。むしろそれは「健全な社会人の姿」なのだ。
悪いのは、その健全を「空気が読めない」と扱い「頑張ってる人」に押しつける風潮なのだ。
「頑張った報い」が、心の傷にならない職場を
あなたの職場にも、こんな構造はないだろうか?
- できる人にだけ仕事が集中する
- 断らない人が、いつも損をする
- 「協調性」が、我慢の同義語になっている
仕事は、誰かの我慢の上に成り立つものではない。声を上げられない人が潰れていくのを見て見ぬふりする職場に、未来はない。
「頑張る」を見直すとき
私は、今日も残業している。
だけど心のどこかで思っている。
「この働き方、いつか変わらなきゃいけない」と。
もしこの記事を読んで、あなたの心にも何か引っかかるものがあったなら
どうか、自分の「頑張り」が報われない構造を、そのまま受け入れないでほしい。職場を変えることは簡単じゃない。でも、自分の価値を守る行動を、少しずつ始めることはできる。